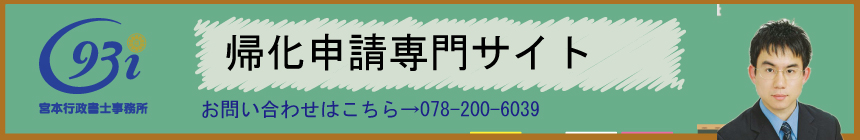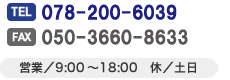帰化申請の申請書の書き方
このページでは帰化をする際の申請書の記載方法等を記載します。なお、帰化の必要書類に関しては、別ページにて説明します。
なお、帰化申請のための必要書類ではありませんが、法務局に相談に行く際の資料として、身分関係図を作成して持って行くことになります。
この表と当事者からの聞き取りにより必要な書類を特定していくことになります。
身分関係図→
目次
1、帰化申請書→
2、親族の概要書→
3、生計の概要書→
4、履歴書→
5、居宅付近図→
6、事業の概要書(事業を営んでいる者)→
帰化申請書のポイント
帰化申請をする際の申請書です。
ポイントは、
1、過去の通称名の有無
2、帰化後の希望する氏名
3、帰化後の本籍地
を抑えることです。
帰化申請書→
1、過去の通称名の有無
結婚、離婚を複数回繰り返している場合、その度毎に通称名を結婚相手に合わせるなどして、変えられている方がいらっしゃいます。
そのような方の場合、通称名を複数有している場合がありますので、申請書作成前に今まで使用していた通称名を書き出しておく必要があります。
2、帰化後の希望する氏名に関して
通常、皆さん現在使用されておられます通称名を帰化後の氏名として使用する場合が多いです。
また、人によっては、「字画」等を占いで決められる方もいらっしゃいます。
ただし、ここで注意しなければならないのが、漢字によっては人名漢字として使用できない場合があるということです。
例えば、藤澤の「澤」という字は人名漢字としては使用できないことになっています。
次に、夫婦一緒に帰化をする場合、夫婦の場合だけ、どちらの名字にするのかを明記(特に、同じ名字の場合が多い、韓国人、中国人の場合注意。)
例えば、李太郎さんと李花子さん夫婦がいらっしゃったとします。
お二人とも通称名を宮本太郎、宮本花子とされている場合、帰化後の名字は宮本としたとしても、この宮本という名字は夫に合わせたものか、妻に合わせたものかをはっきりしなければなりません。
そこで、帰化後の名字は
「宮本(夫の名字)」
というように記載することになります。
3、帰化後の本籍地の場所に関して
通常、皆さん現住所を本籍地とします。
例えば、兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目8-3 402号室でしたら、本籍地と言うのは、
「兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目8」迄となります。
通常本籍地はこのように「~番」までとなります。
次に、名字が同じでなければ、同じ戸籍には入ることができませんのでお気をつけください。
最後に、親と子、そして子の子(親から見た孫)というように、3代続けて同じ戸籍に入ることはできません(3代戸籍の禁止)。
4、写真に関して
撮影後6カ月以内の写真が2枚必要。
2枚必要な理由としては、正本・副本用として必要だからです。
なお、カラーで無くても、モノクロでも可能。
次に、15歳未満の方は法定代理人(通常は父母)と一緒に撮影したものが必要となります。
子供が2人以上いらっしゃる場合は、それぞれの子供と法定代理人の親とで撮影をしておくこと。
5、父母の本籍地
父母の欄には通常、国籍を記入することになるのですが、父母の一方が日本人の場合、戸籍謄本通りに、本籍地を記載することになります。
親族の概要書に関して
親族の概要書に関しては、下記の点をチェックしながら、記載をしていくこと。
親族の概要書に関して→
1、兄弟姉妹の記載漏れや連絡の可否
兄弟姉妹の記載漏れが無いか確認をすること。
各種書類を取得していく中で、思いもかけない兄弟姉妹がいることがあります。
また、同時に帰化意思や帰化への賛否に関して聞いておくこと。
次に、連絡が一切取れない親族がいないかチェック。特に、親で全く連絡が取れない方が要る場合は注意。また、行方不明者がいてもいいが、なぜ行方不明なのかを法務局より細かく聞かれるので注意。
2、婚約者の有無
婚約者がいる場合はきちんと伝えること。
また、結婚等が近いんですと伝えると面接日を早めてくれる場合がありますので、一度ご相談ください。
3、記載方の範囲
申請者以外は、記載をしないこと。
また、申請世帯毎にまとめて記載すること。
(例えば、夫婦で帰化申請する場合、夫を中心に考えると、父母、妻の父母、兄弟姉妹、妻の兄弟姉妹等。)
次に、離婚した前夫or前妻がいる場合は、その者も記載もすること。
帰化申請時に思い出したくない過去や配偶者に言っていない場合もありますが、調べられると分かってしまいますので、正直に事実として申請書に記載しておいた方がよいでしょう。

生計の概要書に関して
下記では帰化申請書のうち、生計の概要書に関して、説明します。
生計の概要書→
1、同居の親族の仕送り先の方も記入すること。
夫婦子供だけでなくても同居の親族でも当てはまる(姉と妹等)
また別居しているが仕送りをしている場合(子供が学校の近くに部屋を借りている場合、学費や生活費を主たる扶養者が出している場合)は同一世帯と考えられ、生計の概要書に当該費用等も記載しておくこと。
なお、たとえ家族であったとしても、それぞれ独立に生計を営んでいる(生活をしている者)は生計の概要書は別々もしくは、記入しなくてもよい。
2、月収は手取額で記載すること。
月収は社会保険料などを除いた手取り額で計算し、記載すること。
ここで、手取りとは、給与明細書欄では支給額と書かれている部分です。(具体的には給与収入から社会保険料、所得税等を差し引かれた後の手元に残る金額を言います。まさに手取りという表記通り、実際に通帳に振り込まれている金額等を記載することになります、)
当該手取り額等の確認はそれぞれが月末にもらっている給与明細書にて確認をすること。
3、就職日の確認
生計の概要書作成中、備考欄には会社員の場合就職日、経営者の場合、経営を始めた日を記載することになりますので確認しておきましょう、
4、1,000円未満は切り捨て
社会保険料や水道光熱費などを出していくと細かい数字が並ぶことになるかともいますが、数字を記載するに当たって、1,000円未満は切り捨てて記載することになります。
例えば、水道光熱費が13,450円かかっている場合、13,000円とすることになります。
5、手取りと支出がいこーるになるように
最終的には、手取りの金額と支出とが=(イコール)になるようにきさいします。
もちろん、月によって支出が多い月、あるいは少ない月。
ボーナスなどで手取りが多い月、もしくは少ない月があると思いますが、直近(一番近い)月のものや平均した金額を記載して頂くことになります。
6、借金の記載は正直に正確に
借金の記載を隠したがる、もしくは過小に申告される方がいらっしゃいます。
どんなに借金があろうと、きちんと返済できているのであれば、帰化申請の許可、不許可に影響はしませんので、事実を記載していってください。
7、株券等に関して
自分は株をしていない方であっても、会社の持ち株会に参加しており、退職時等に返済をしてもらうという形態を取っている場合があります。
このような場合でも立派に株をもっていることになりますので、記載時にはお気をつけください。
履歴書に関して
履歴書への記載に関しては、小学校から現在まで記載する必要があり、人によっては、思い出して書いて行くまでに相当日数係る場合があります。
そのため、できるだけ早いうちから、作成に取りかかりましょう。
帰化申請のための履歴書→
1、身分関係に関する注意点
履歴書中には、身分関係(結婚、離婚)や父母の死亡等も記載しておく必要があります。
このうち特に離婚歴などを隠しておきたい方もいらっしゃいますが、公的な書類を取ればわかってしまいますので、事前に現在の配偶者には説明しておきましょう、
また、婚姻前の同居(同棲)期間等に関しても事実婚として記載をしておく必要があります。
2、閉鎖された外国人登録原票にて最終チェック
次に、身分関係や住居の変更等に関して、最終的には、「閉鎖された外国人登録原票」にて確認をする必要があります。
ただし、閉鎖された外国人登録原票には、通学した小学校~大学等の学校名はありません。また、
また、役所には届け出ずに、引越しをしている場合もあるので、公的書類に出てこないため、きちんと確認をしておきましょう。
3、渡航歴に関して、
日本人の配偶者の方や、日本で生まれ育った外国人の方は、3年間。
それ以外の方は5年間分必要となります。
4、仕事に関して
就職の際の具体的な職務内容(営業等)を記載しておくこと。
この職務内容を忘れてしまっている場合がありますので、要注意が必要です。
居宅付近図
居宅付近図に関しては特に難しくはありません。
同居者等に誰がいたのか?(親族以外も含む)をきちんとまとめておくことが肝要です。
居宅付近図→
事業の概要書に関して
事業の概要書に関しては、基本的には、直近の決算書(収支内訳書)等を基に作成していくことになります。
具体的には下記の通りです。
事業の概要書→
法人の決算書の場合
・従業員数等に関して聞いておくこと。源泉徴収簿等があれば、当該書類を基に作成していきます。
なおここでいう源泉徴収簿というのは、毎月記載され、年末調整等の計算をする書類のこと。
・借入等に関して、借入年月と返済方法、そして、借入の目的は上記書類上不明なので、会社に備え置かれている書類等で確認しつつ作成していくこと。
・取引先に関しては、決算書の売掛金や買掛金の部分である程度分かりますが、基本は、取引先の名称、所在、電話番号、年間取引額、取引内容、取引期間を会社に備え置かれている他の書類で確認すること。
・事業年度は法人登記簿謄本に記載されているので確認のこと。
・許認可を得て仕事をしている場合は許認可番号と証書の写しが必要なので注意を要する。
個人の決算書の場合
上記法人の決算書の場合に加えて、開業年月日、事業用財産、借入欄の全ての部分、取引先全てを備え置かれている他の書類で確認すること。
なお、営業資本の欄に関して、通常は元入れ金を記載するが、65万円控除ではなく、10万円控除受けている場合で、貸借対照表を作成していない場合は、別途当該営業資本に関して確認しておくこと。例えば、1月1日時点での事業用の預貯金の残高等で判断するなど。
- お客様の時間をとらせません。
-
会社員の方、会社経営者の方のお時間を取らせません。
くわしく見る
- 不許可の場合は全額返金
-
仮に申請後不許可になった場合は、全額返金すると共に国籍を喪失した場合は、当該国籍を復活させる手続きを行います。
くわしく見る
- 帰化に必要な書類
-
帰化に必要な書類を紹介します。
くわしく見る
ご自身で一度作成にトライしてみてください
- お問い合わせから申請までの流れ
-
お問い合わせから申請までの、
くわしく見る
流れを説明しております。